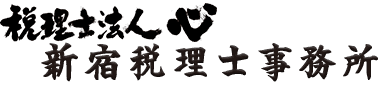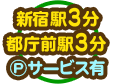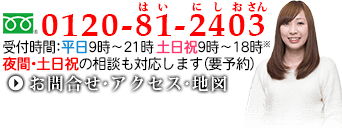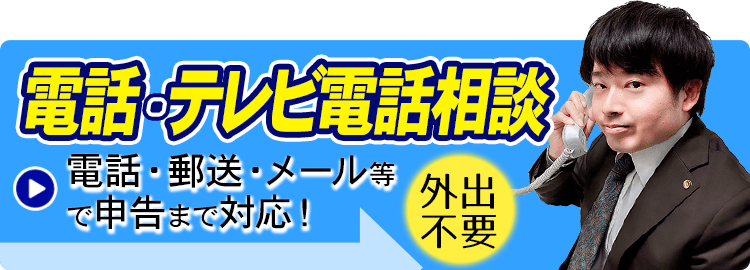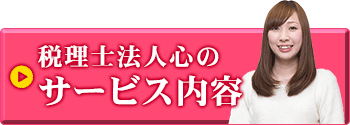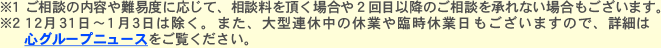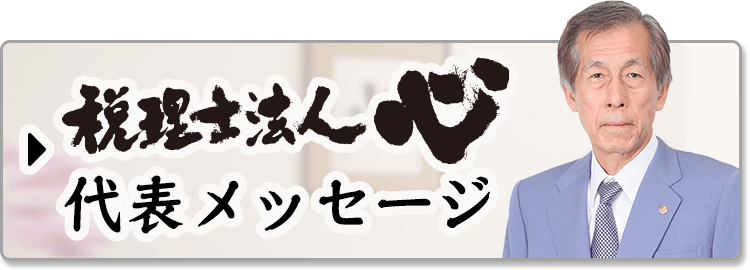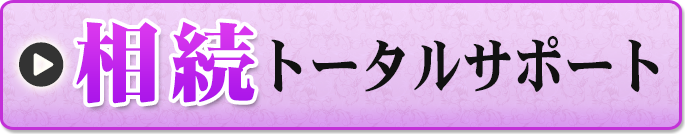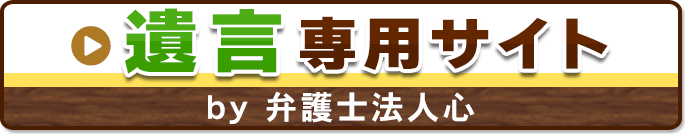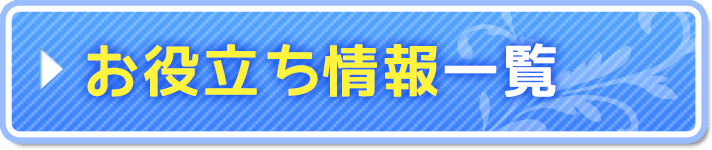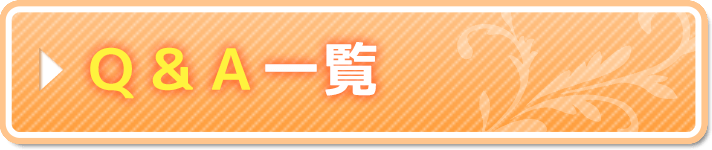法人成りに適したタイミングとは
1 法人成りとタイミング
個人事業主が事業を拡大していく中で、よく検討されるのが法人成り、つまり、個人事業の法人化です。
法人成りとは、これまで個人事業として運営してきたビジネスを法人(株式会社や合同会社など)の形に移行し、法人格を持たせて事業を行うことを意味します。
法人成りにはさまざまなメリットがありますが、その反面、税理士報酬といった費用や法人設立及び法人格を継続させる手間というデメリットもかかります。
したがって、いつ法人化するべきかというタイミングの見極めが非常に重要です。
ここでは、法人成りに適したタイミングについて、税務・経営・信用力など複数の視点から解説していきます。
2 法人成りと事業の所得
最もよくある法人化のタイミングは、課税される所得つまり利益が増えてきたタイミングです。
日本の所得税は累進課税であり、利益が大きくなるほど税率も高くなります。
所得税と法人税の税率の比較をすると、所得税の最高税率は45%で、住民税を含めると最大55%の税率です。
一方で法人税は、中小企業なら実効税率が約23~30%程度となります。
たとえば、個人事業の所得が年間695万円を超えると年間900万円までは所得税の税率は23%、住民税も含めると33%となり、上記年間所得を安定して超えてくる、つまり平均年間800万円を超えてくると、法人税の実効税率と比較して、法人化した方が税率が低くなり、手元に残る資金が増える可能性が高くなります。
また、法人化することで役員報酬や経費の調整など節税の幅も広がるため、課税所得が年700万円を超えたあたりから法人化を検討すると良いとされています。
3 法人成りと経費
法人には、個人事業主では認められない節税策や経費処理が可能です。
例えば、役員報酬が個人事業主には認められない節税策になることがあります。
具体的には、役員報酬は法人の経費にできるため、青色専従者の要件を満たさないような親族も役員にすることで人件費を経費にし、所得を分散させて所得税を節税することが可能です。
また、退職金制度があります。
個人事業主には似たような制度はあるものの、退職金という仕組み自体はありません。
法人は役員に対して退職金を支給でき、役員は退職金控除を受けることができます。
また、生命保険の活用も考えられます。
法人が契約者及び保険料負担者の保険契約を結ぶことができ、保険料の一部を損金算入できる商品も多いです。
他にも、社宅制度の利用が考えられます。
法人契約の社宅を一定要件のもとで提供し、実質的な生活費を抑えることが可能になることもあります。
このような個人事業主ではできない経費処理を活用できるのは、経営者にとって大きな魅力です。
上手に経費を活用したいと考えるようになったときが、法人化のひとつのタイミングと言えるでしょう。
4 法人成りと信用力
法人は、個人事業に比べて社会的信用が高いとされます。
例えば、新規の大手企業との取引開始、金融機関に融資の申請をする、事業提携や出資を受ける場面等、事業の規模が拡大し、外部との関係で信用力が求められるようになったときが法人化のタイミングです。
事業規模が拡大し、従業員を多く雇用したいときは、個人事業より社会的信用が高い法人になっておくことが重要となります。
5 法人成りと税理士
法人成りには税務面でのメリットだけでなく、信用力の向上等の利点があります。
とはいえ、法人設立には登記費用や顧問税理士の費用、社会保険料の負担など、コストも発生します。
そのため、どのタイミングで法人化するかは、単なる利益の増加だけでなく、将来のビジョンや経営体制の変化と合わせて慎重に判断する必要があります。
最終的には、事業の性質や経営者の考え方によって最適なタイミングは異なります。
法人化を検討している場合は、税理士などの専門家に相談し、税務・経営・信用力等の側面から総合的に判断することが失敗のない法人化への第一歩となると思われます。